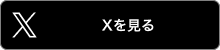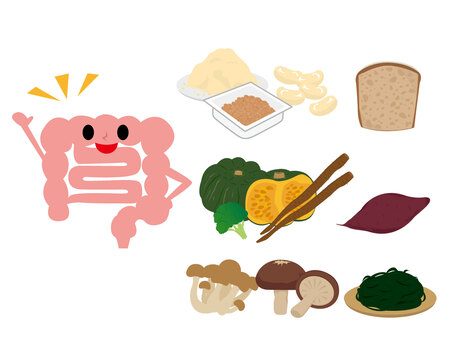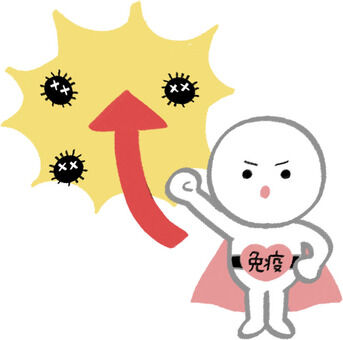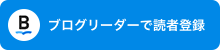「食物繊維」は整腸だけにあらず
こんにちは٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
四つ葉のくまさんことよつくまです
本日もよろしくお願いいたします。
「根菜類」
野菜のうち土壌中にあるものを食用するものの総称
→Wikipediaより引用
ありがたく大地の恵みを頂きたいものです。
本日は、
土の匂いを頂く…「食物繊維」の塊「ごぼう」です。

画像はイメージ フリー画像です
(アスリートにもおすすめできます)
「ごぼう」と「新ごぼう」
【ごぼうの基本情報】
・キク科
・ゴボウ属
・ユーラシア大陸北部原産

画像はイメージ フリー画像です
(出来れば「泥付きごぼう」を洗いたい)
「ごぼう」と言えばシャキシャキとした食感。
「きんぴらごぼう」は最もポピュラーな調理方法です。
・炒めもの
・煮物
・サラダ
・天ぷら
など使い方は様々です。

画像はイメージ フリー画像です
(かき揚げも美味しい)
「かぶ」など同様に「旬」にあたる時期が2回あるのも特徴です。
1回目 ⇒ 4~5月
2回目 ⇒ 11~1月
1回目の早採れの「ごぼう」を、
「新ごぼう」
「春ごぼう」または「夏ごぼう」
などと言います。

画像はイメージ フリー画像です
(「新ごぼう」のイメージ)
「新ごぼう」は成長しきる前に採取します。
その為にとても柔らかいのが特徴です。
「ごぼう」が苦手な方は、
「独特の大地の香りが苦手」という方もおられます。
その点「春ごぼう」は香りも穏やかで食べやすいです。
「ごぼうサラダ」などにして頂くととても美味しく味わえます。

画像はイメージ フリー画像です
(「マヨネーズ」との相性も抜群です)
「腸内環境」を整えて発がん性物質を吸収排出
【主な栄養素】(代表的なもの)
・カリウム
・マグネシウム
・カルシウム
・食物繊維
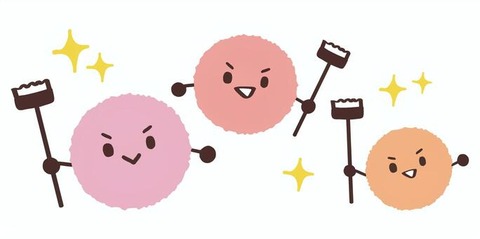
画像はイメージ フリー画像です
(「腸内環境」を整えます)
【特筆すべき栄養素】
「ごぼう」=「食物繊維」というくらい、
「食物繊維」を豊富に含みます。

画像はイメージ フリー画像です
(「腸活」にもってこいの「ごぼう」)
水溶性の「イヌリン」
不溶性の「セルロース」
共に豊富に含みます。
血中コレステロールの値を下げ、
「腸内環境」を整えてくれます。
特に「リグニン」という物質は発がん性物質を吸収排泄します。
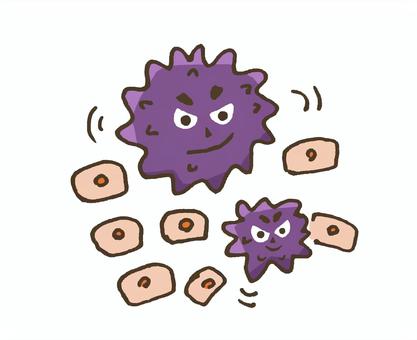
画像はイメージ フリー画像です
(恐ろしい「がん」を排出してくれる)
アク抜きは不要?
【調理のポイントなど】
最近では「ごぼう」の「アク抜き」は不要といわれています。

画像はイメージ フリー画像です
(たわしなどで汚れをこそげ落とします)
たわしなどを用いて、泥を洗い落とします。
一般に知られている方法である、
・酢水でさらす
・皮を全て剥く
を行った場合、
せっかくの「ポリフェノール」を大幅に捨ててしまう事がわかってきました。
栄養成分を捨てることにつながるので、たわしなどできれいに洗う程度で充分です。

画像はイメージ フリー画像です
(「アク抜き」をする場合は短時間で)
土の匂いが気になる方は軽く「アク抜き」をしても構いません。
「アク抜き」は美味しく頂く方法でもあります。
仕上がりが白く美しくなるので、
調理内容により使い分けましょう。
「惣菜」や「お弁当」にもピッタリ
【おすすめの調理方法】
「ごぼうと切り干し大根しいたけの炒め煮」
いわゆる「きんぴら系」のおかずになる「惣菜」です。

画像はイメージ フリー画像です
(お弁当のおかずにもピッタリです)
【作り方】
・ごぼうは皮ごとささがきにします
・切り干し大根を裏書き通り戻します
・しいたけはスライスしておきます
・ごま油などでしっかり炒めます
・酒、みりん、だし汁、しょうゆ、砂糖を入れて炒め煮します
・水分がなくなってきたらごまを混ぜ合わせて完成
簡単ですが常備菜や副菜などに大活躍します。
調味料は「めんつゆ」で代用可能です。
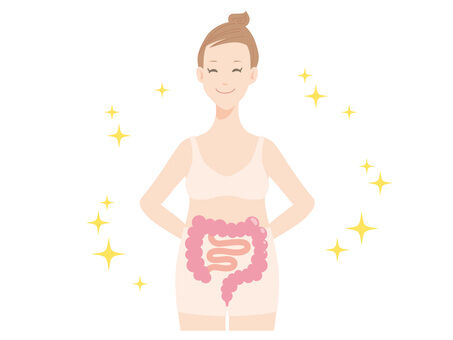
画像はイメージ フリー画像です
(「腸活」は全身の健康維持に繋がる)
美味しく頂けて、
・腸活
・がん予防
ができる「優れもの」です。
ぜひお試し下さい。
海外ではほとんど食されない野菜
ごぼうは「食物繊維」の塊です。
便秘気味の方、
血糖値の高い方(糖尿気味の方)は特に積極的に取りたい野菜です。
便秘解消 ⇒ 美肌
にもつながります。

画像はイメージ フリー画像です
(漢方としての側面もある)
ちなみにあまり海外では食されていません。
よく食べるのは日本と台湾…中国では漢方薬として扱うそうです。

画像はイメージ フリー画像です
(特に欧米の方は食べないとのこと)
欧米の方から見ると「樹の根」にしかみえない…のが理由だとか。
「鶏肉」などとも非常に相性がよく、
食べ合わせも良い組み合わせです。

画像はイメージ フリー画像です
(「鶏ごぼう煮」はアスリートにもおすすめ)
成人病予防や便秘予防など上手に摂りたい野菜です。
身体を温める効果のある根菜たち、
上手に大地の恵みを頂くことにしましょう。
よつくまがお届けいたしました˚*・.。 ꕤ
(2024.3 加筆修正)
合わせて読みたい記事です
ご登録頂ければ嬉しいです


※ご登録頂くと記事が更新された際にアプリで通知が届きます。
見逃したくないブログやよく閲覧するブログなどに便利な機能ですꕤ
X(ツイッター)のんびり更新中です